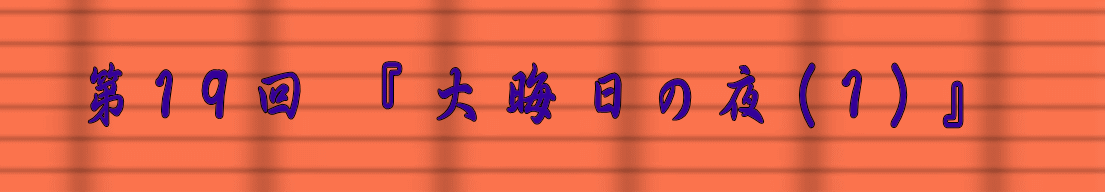校長コラム PRINCIPAL'S COLUMN
30.12.1
校 長 坪 井 基 紀
いよいよ今年もあと一ヶ月となりました。昨年度、秋の全校集会では落語「芝浜」に出てくる大晦日の夫婦の会話を取り上げました。拾ったお金が夢だったということを知った魚屋の勝五郎が心を入れ替えて一生懸命に働き、三年経ち自分の店をもてるようになったという話です。その最後の部分で、三年前に拾ったお金を内緒で奉行所に届け、拾ったことを夢だったことにしたという妻からの告白をその年の大晦日に聞きます。苦労せずに得た大金をなかったことにしてくれたおかげで三年間真面目に働くことができたと、勝五郎は妻の行動に感謝をしました。夫と妻のほのぼのとする会話です。
大晦日の話は他にもたくさんあります。今、私の頭に浮かぶのは30年も前に大評判になったのですが、いろいろな事情から今は話題にも上らなくなった話です。記憶を辿り少しだけ紹介します。ある年の大晦日の夜、札幌のあるおそば屋さんへ季節はずれの半コートを着た女性が二人の幼い子どもを連れてやってきました。注文したのはかけそば一杯だけでした。何か事情があるのではと察したそば屋の主人は、母子にわからないようにそばを一玉半に増量して母子に出しました。店のすみのテーブルに出された一杯のかけそばを、母親と幼い兄弟は額を寄せ合っておいししそうに分け合いました。実は、その家族は父親を事故で亡くしており、大きな借金をかかえていました。そのため、母親は朝から夜遅くまで働き、兄は朝夕の新聞配達を、弟は夕飯のしたくをするといったように毎日が大変な日々で、三人にとってこの店のかけそばを食べることが、年に一度の贅沢だったというわけです。その年から、この母子は毎年大晦日の夜にやってくるようになり「おいしいね」「今年もこのおそばが食べられてよかったね」「来年も食べられるといいね」と、そんな会話を三人でしていました。店の主人にとってもこの母子へそばを出すことが、大晦日の恒例となっていました。しかし、ある年を境に母子は来なくなりました。それでも、そば屋の主人は毎年、母子のために「その席」を空けておきました。そして時は流れて、最初に母子が店に来てから14年後の大晦日の夜、医者と銀行員になった二人の子どもが母親と一緒にやってきて、最高の贅沢を計画したと言い三杯分のかけそばを注文するという話です。
大晦日の夜は、その一年に自分がどれだけがんばったのか振り返るよい時間であると思います。もう少し言えば、苦しかったことや辛かったことをなんとか乗り越えて一年の最後の時間に近しい人と話しながら過ごすことは最高の贅沢ではないでしょうか。私はそういう時間に生きている喜びを感じます。そして、来年もがんばれよと励まされます。